下水道管路の維持管理時代
における新技術
-管清工業株式会社-

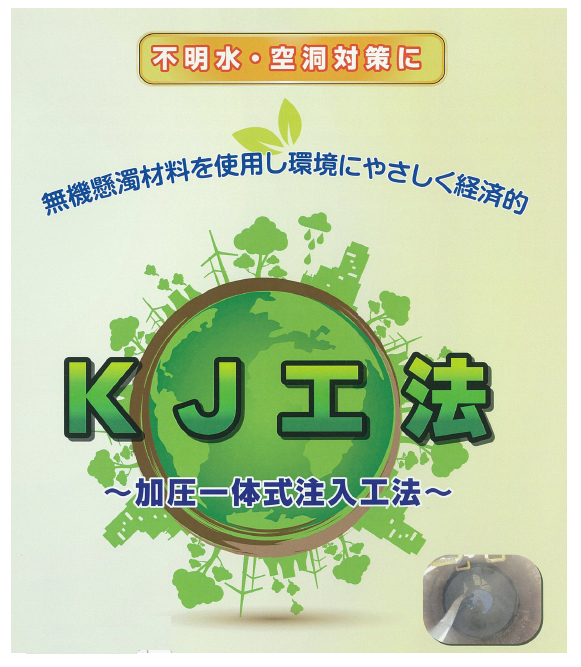
社会基盤整備の新規建設の時代から、維持管理の時代に入った今日、膨大な既存施設を抱えた状況下での維持管理は多くの課題を抱えています。既存施設の機能を維持したまま、施設の延命化・長寿命化に最も適切な対策は何なのか、を選択して実行していくことは重要な責務です。 これまでの下水道整備により、管路延長は約46万kmに達しており、耐用年数を超える老朽管きょは平成24年度末で約1万km、10年後には約4万km、20年後には約11万kmに増加すると予測されています。これらの膨大な管路の維持管理は、下水管路の老朽化に起因する突然の道路陥没などに迅速に対応する「発生対応型」から、定期的に調査して市民生活に直結する深刻な問題を未然に解決する「予防保全型」へと転換しつつあります。 当社はこのような状況において、維持管理に有効な新技術を発信してまいります。
次世代の管路水密性試験の新技術「エレクトロスキャン」
テレビカメラ調査は、視覚調査により腐食やクラック等の管の不具合を劣化程度に応じてランク付けする方法として一般的に行われています。一方でオペレーターが見逃した、あるいは発見できなかった管、継手部、取付管接合部の不具合を事後評価することはできません。予防保全を行っていく上で、基礎となる管路データに不備が生じる可能性もあります。
エレクトロスキャンは、管路施設内の異常を「電流の力」によって探し当て、同時に数値化することによって、その程度を評価することができ、従来の視覚中心調査方法とは一線を画するものです。特に、視覚調査では見つけにくい破損やパッキンずれなどを発見することができ、しかも、それには特段の熟練を要することなく、客観的に評価できます。 本技術はアメリカに本拠をもつエレクトロスキャン社によって開発されました。アメリカではASTM F2550-13「管壁を貫通する電流の変動の測定により下水道管の水密性異常を探査する実施基準」に準拠する調査方法として浸透しつつあり、イギリスをはじめとしたヨーロッパやオーストラリアでも実施され、海外では高い評価を受けています。 この新技術を利用することにより、点検・調査のスピードアップを図ることができ、予防保全にとっての有効なツールとなると期待されています。
環境に優しく経済的な加圧一体式注入工法「KJ工法」
KJ工法は、修繕改築工法の分類上では加圧一体式注入工法と定義され、1962年以降で10都22都市1団体に導入されており、平成25年度末までの施工実績は約100kmとなっています。
KJ工法は、対象スパンの本管や取付け管の管口に止水栓を設置し、密閉状態にしたうえで、セメントミルク等の注入剤を対象スパン内に加圧充填します。これにより、クラック、破損、目地隙間などの密閉性不良箇所への止水効果が期待されます。さらに、管外へ注入剤が浸透することで、空洞充填の効果も期待できます。
KJ工法では本管・取付け管・マンホール・副管の全体同時施工が可能なため、部位ごとに必要であった従来の管更生工法と比較し、トータルコストの削減が図れ、経済的に後期の短縮化が実現することから、良い物は長く使うというストックマネジメントに寄与することができます。また、工事の専有面積が少なく、騒音や振動等の発生が少ないことから、近隣への影響を最小限にすることが可能です。
いずれの工法も、「資料ダウンロード」ページより資料請求が可能です。